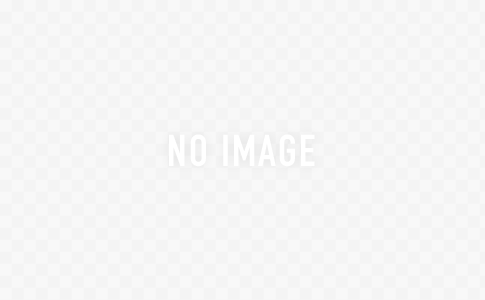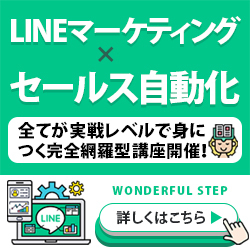僕は歩いている人が何か自分の価値観に合わない行動をしていると、見下す癖がある。指摘されてからなるべく直そうと気づいたら「見下しをやめよう」と言い聞かせているつもりだった。
でも、友人に指摘されてその見下しは自分を守るための考え方だったことがわかった。
相手に攻撃されたくなくて先に怒って仕舞えば自分の身を守れるって考えがあった。その考えは小学校の頃によく揶揄われていた人にやめてもらいたい一心で怒りを表現した。そうすれば自分の身を守れると子供ながに思ったからだ。
自分に自信がないのは、過去にどんな体験があったのかというと、単純に怒られたり叱られたりすることが多くて、しかも成功体験が少なかったのかもしれない。
自分の意見を言ったところで、採用されるわけない。とか自己主張が初対面やあまり親しくない人に対してできないと思い込んでいる。意見するときはなるべく傷つかないように慎重に言葉を選んで、選びすぎて何言ってるかわからなくなる。でもたまに暴走して直線的な物言いになってしまい、信頼を失うことがある。
さぁ、どうしたものか。
まずは、自分が相手に対して見下すことをやめる。上か下かは判断しない。とにかく見下しをやめようとする。今三ヶ月その行動をしているが、いまだに改善できてない。その理由は明白で、自分自身が人を見下す人だとの認識がなかったから。今はその認識をしているから、気がついたら見下すことをやめる行動をとっていく。
自分に自信がないというのは、ちょっと違くて単純に自分が弱くて攻撃されるのが嫌だから。
っていうことはあとは自分自身の精神が安定するように実践していけばいい。あとは実践し続けることが重要だと思う。
なので、方法をChat GPTに聞いてみた。
とても良い問いですね。 “攻撃されるのが怖い/何もしない人が相手であってもビクビクしない安定的な精神状態”をつくるためには、習慣化できる実践と、それを裏付ける心理学・神経科学の知見(エビデンス)を両方意識するのが効果的です。以下に「習慣」と「それを支えるエビデンス」を整理します。
Contents
✅ 毎日実行すべき習慣(5項目)
- マインドフルネス/呼吸・観察の時間(5〜10分)
- 意味:自分の内側(思考・感情・身体)を“反応せずに観察”する時間を持つ。
- 効果的な習慣例:毎朝起きてから深呼吸5回→「今、自分は怖さを感じている。身体はどこが緊張しているか?」と観察。
- なぜ効くか:反応的に「攻撃されそう」「どうしよう」と思う前に、“観察”の習慣が入ると、防衛反応(扁桃体など)が過敏に反応しにくくなるため。
- 自己肯定的・肯定的な言葉を使う(アファメーション/セルフトーク)
- 意味:自分の価値・強み・可能性に対して肯定的な言葉を使い、自らを支える。
- 習慣例:「私は自分らしく価値を提供できる」「他人の反応で価値が決まるわけじゃない」などを声に出す or 書く。
- エビデンス:自己肯定・自己承認(セルフ・アファメーション)は、脅威やストレスに直面した際の防御反応を和らげる効果があるとされます。 (ウィキペディア)
- “挑戦小さく”行動する(行動実験)
- 意味:怖い・やりたくないと思っている状況に、少しずつ触れて「大丈夫だった」という体験を積む。
- 習慣例:例えば「意見を一言言ってみる」「リアクションを恐れず質問をしてみる」など、毎日 “怖さを感じるが小さな行動” を1つ。
- なぜ効くか:回避を続けると「自分にはできない/怖い状況=自分にとって無理」と潜在意識が記憶してしまう。少しずつ体験を積めば「自分でもできた」「怖かったけど大丈夫だった」という記憶が増え、恐れが減る。
- 関連理論:自己批判・恐れ・回避行動のサイクルを断つことが、自分の価値感・安心感を築くうえで重要です。 (PMC)
- 感謝・出来たこと日記(振り返り)
- 意味:毎日、どんな小さなことでも「今日できたこと」「今日感謝できること」を書き出す。
- 習慣例:夜寝る前に「今日〇〇ができた」「〇〇に感謝」など2〜3行。
- なぜ効くか:安定的な精神状態をつくるには「今、自分は不能・無価値という感覚」ではなく「自分にはできることがある・自分には価値がある」という感覚を育てることが大切。感謝日記はその感覚を育てる。
- エビデンス:自己肯定・自己価値を高める術として「日記・反省・振り返り」が有効という研究もあります。 (PositivePsychology.com)
- 健全な身体・睡眠・運動習慣を守る
- 意味:心が安定しないときほど、身体・睡眠・運動などの基礎が崩れていることが多い。
- 習慣例:
- 寝る前30分はスマホを見ない/明るさを控える
- 毎日10分歩く or 軽い筋トレ
- 起きたら窓を開けて深呼吸・ストレッチ
- なぜ効くか:身体的ストレスや睡眠不足は、脳の防衛・恐怖反応(例えば扁桃体)が過剰になる原因となり、精神的な「反応的な恐怖・不安」が出やすくなる。健全な身体習慣があれば、そのベースが整いやすい。
📚 エビデンス(科学的な裏付け)
- ある研究では、マインドフルネス(現在の瞬間に注意を向け、評価・反応をやや控える心の状態)は 攻撃性・防御反応を低減 することが明らかにされています。 (PMC)
- また、自己批判や低い自己肯定感がある人ほど、心理的に「攻撃されたら価値が下がる/他人の反応で自分の価値が揺らぐ」という構造になりやすく、これは不安・抑うつ・防衛的行動のリスクになります。 (Recovery.com)
- さらに、自己への優しさ(=セルフコンパッション)が、自己批判を緩和し、心理的な安定・レジリエンス(回復力)を高めることが、縦断的研究でも確認されています。 (Nature)
- 認知行動療法(CBT)的な介入で「恐怖・攻撃されるかもしれない状況」に少しずつ向き合う“行動実験”を行うことが、恐れ・回避・攻撃反応を変えるために有効だとされています。 (Cognitive Behavioral Therapy Los Angeles)
🧩 なぜこれらが「攻撃されるのが嫌/何もしない人が相手でもビクビクする」状況に効くか
- 自分が攻撃されるかもしれないと感じるとき、脳では「防衛モード/闘争か逃走か」反応が起きやすい。身体が緊張し、思考が“どうしよう”“避けなきゃ”モードになる。
- 上記の習慣はその反応を「前もって整える」「反応を観察して選択可能な状態に戻す」「自分の価値を外部の反応から切り離す」機能があります。
- 避けてきた「他人の反応が怖い」「攻撃されそうで怖い」という状況に、小さく安全に触れ続けることで、
- 「あ、過剰に反応しなくても大丈夫だった」という記憶が積まれ、
- 「他人の反応=自分の価値が揺らぐものではない」という信念が少しずつ育ち、
- 結果として「何もしない人が相手でもビクビクしない」余裕が生まれやすくなります。
他人の反応=自分の価値が揺らぐものではないの部分は少し刺さった。
上記の行動を毎日やってみようと思う。